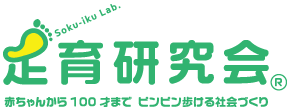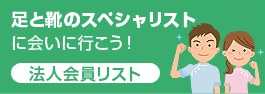コラム

プロフィール
高山かおる
- 足育研究会 代表
- 済生会川口総合病院皮膚科部長
- 東京医科歯科大学大学院 皮膚科学教室特任講師
- 医学博士
- 皮膚科専門医
- フットケア学会評議員
- 日本トータルフットマネジメント協会理事
- 接触皮膚炎・皮膚アレルギー学会評議員
爪切り難民と爪甲除去(麻酔を要さない)60点(2020/09/04)
医学書院臨床皮膚科
「マイオピニオン」
済生会川口総合病院皮膚科
高山かおる
はじめに
当たり前のことであるが、爪母を失っていなければ爪は生涯において伸びる。足の爪を切ることは、手が足に届く姿勢をとることができ、足先をみることができ、爪切りを操作することができれば困ることはないが、どれかそのうちのひとつでも困難になると、自分自身での足の爪切りはできない。
おなかが邪魔するなど体形の変化によって物理的に手が届かなくなることもあるし、関節の柔軟性が失われる場合にも届かなくなる。目がよく見えないと細かい作業は難しくなり、力がはいらないと爪切りもうまく使えない。また爪の変形によって難しくなる場合も多い。
爪が自分で切れないときの選択肢
爪が自分で切れなくなった「爪切り難民」はどうするのか。①放置する、②家族が切る、③介護者が切る、④看護師が切る、⑤医師が切るなどの選択肢が挙がるかと思う。
それぞれの選択について、利点と問題点について考えてみる。
①放置する
高齢者の足の爪には高率に異常があり、本人家族が爪を切れずに放置されているという調査結果がある。血管閉塞などの合併症があれば、壊疽のリスクとなるのはもちろんであるが、あらぬ方向に伸びた爪が隣の趾に傷をつける、靴を履くことが困難となり、自然に外出を自粛し、フレイルに直結する問題となる。
それ以上に非常に不衛生な状態となり、人としての尊厳を著しく傷つける。つまり決して放置はできない。
②家族が切る
これができれば一番望ましいが、そもそも家族がそばにいないことも多い。さらにそばにいる状態であっても上述したように変形した爪や伸びすぎた爪に家族は戸惑う。
本人が隠して見せないということもよく聞く。
③介護者が切る
爪切りは「爪に異常がなく、本人の様態が安定している場合に限り」介護職にも認められている行為である(厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)参照)。
ところが高齢者の足の爪には異常が多いため、この通りに解釈すると、介護者が爪を切ることに躊躇することは当然多い。
④看護師が切る
「爪ケア」は看護行為の中では「基本的生活行動の援助」の領域に分類され、「療養上の世話」として看護師が主体的に行うことができる。
つまり、爪切りは看護師が行うのが望ましいのだが、2007年に北九州市の病院で、入院中の高齢者の患者に対し、肥厚した足爪をニッパーで切り取るとした行為が「傷害罪」にあたるとして看護師さんが逮捕・起訴されてしまうという事件が起きた。
最終的にこの看護師さんは無罪となったのだが、異常な肥厚爪を整えるときに、「傷害罪」を問われたり、また診療の中の「医行為」なのかが争点となり、この事件をきっかけに爪ケアを行うことにリスクを感じている看護師は今でも多い。
⑤医師が切る
ご存知の通り、爪甲白癬または爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものに対して爪甲除去(麻酔を要さない)60点が算定できる。
そのため、以上に述べた選択枝の中で肥厚した爪を切るべきなのは医師である。
しかし、手が届かないから、うまくできないから爪を切ってほしいというのは医療行為ではない。また肥厚した爪を何本も切ったり整えたりするのは大変な労力で時間もかかり、60点にはとても見合わないこともあり、積極的に医師が行うモチベーションは沸きにくい。
爪切り難民を作らないための策
こう書きだしてみると、伸びた爪といつも戦っている身としては絶望的な気分に陥る。
しかし難民化は高齢者の増加とともに進んでおり、このままにはできない。いくつかの解決策になると思われることや、現在実際に進んでいることについて紹介する。
1フットケア指導士の育成
(旧)日本フットケア学会(現日本フットケア・足病医学会)では足のケアを必要十分に、そして安全に行う技術を医療現場に提供できるフットケア指導士を養成している。
2019年6月の時点で1506人を認定している。指導士は医療現場、介護現場で活躍している。
2爪切りの自費診療
当科で開いているフットケア外来では自費診療を行っている。医師の指示のもと、フットケアを学んだ看護師が患者一人当たり30分程度、週1回(6人程度)外来を開催している。
多くの患者には対応できないため、受診間隔があいてしまうという問題はあるものの、患者は安心でき、そして医師としてもありがたい診療補助である。
3フットケアスペシャリストを活用する。
海外には国家資格をもったフットケアの専門家がいる国もあるが、日本でも独自に海外などの技術を勉強され、日本にその技術をもってきてフットケアスクールを開いている方々がおり、民間のフットケアスペシャリストが育成されている。またこれらのスクールではフットケアの技術をより専門的に対応できるようにとなりたいと思っている看護師や介護士に対しても技術を勉強する機会を与えている。
しかしここでも問題になるのが、どの爪なら切ってよいかというその境目だ。
この問題に真剣に向き合った高齢者のフットケアを提供している事業者(https://asi-care.com/)が、2017年にこのグレーゾーンの解消を行い、高齢者介護施設と業務提携契約を行い、医師が施設入居者の身体状態を確認し、治療の必要がないと判断した部位(医師が事業者に対し書面で情報共有)に対して、医師でない者が、「軽度のカーブ又は軽度の肥厚を有する爪について、爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること」に関しては医師法に触れないという回答を経産省から得た。
医療-民間連携を行い、フットケアスペシャリストが高齢者の爪切りをしてもいい場合があるというお墨付きであり、すばらしい難民対策になっている。
同じように介護士が爪切りを安全に行う技術を身につけることができれば、そもそも地域の中での医療連携は確立されているため誰もが活用しやすいことを生かそうと、「フットヘルパー」(https://www.foot-helper.com/)の育成にご尽力される方もある。
おわりに
とかく見逃されがちな爪のトラブルに向き合おうと思うと、このように様々な課題が挙がる。
今回紹介できなかったが「薬局での爪切り」なども開始しており、変化する時代に対応し、より多くの人に健康な状態でいていただくために、「地域」「他業種連携」などをキーワドとして、一皮膚科医として何ができるのか考える日々である。
コラム一覧
- 巻き爪の論文について解説します 2/2(2023/12/08)←NEW!!(今井亜希子)
- 巻き爪の論文について解説します 1/2(2023/12/01)(今井亜希子)
- 「靴型装具」とは?(2023/09/12)(大沼幸江)
- 夏のサンダルの選び方(2023/05/31)(山口久美子)
- 「介護現場でのフットケア」の実際(2023/05/22)(奥田昌子)
- 「介護現場でのフットケア」の問題点(2023/05/16)(奥田昌子)
- 足のサイズに合った靴下選び(2023/03/31)(藤井恵)
- 100円のインソール(2023/01/17)(吉本錠司)
- インソールとは(2023/01/11)(吉本錠司)
- 履く前に靴の中を確認しよう!(2022/11/21)(山口宏二)
- タコやウオノメの位置でわかる、歩き方のクセと改善ケア方法2(2022/11/11)(小暮祐輔)
- 天狗の高下駄と裸足の感覚を都会でも(2022/10/17)(佐藤進一)
- タコやウオノメの位置でわかる、歩き方のクセと改善ケア方法.1(2022/09/28)(小暮祐輔)
- 学校生活での1足制について(2022/08/23)(寺杣敦行)
- 子供のサッカーシューズは足を育てるのか(2022/08/09)(石原智光)
- 子供のサッカーシューズは足を育てるのか(2022/07/27)(武田剛)
- なぜ今の上履きが昔のまま残っているのか?(2022/07/19)(石原智光)
- なぜ今の上履きが昔のままなのか(2022/07/08)(武田剛)
- 高齢者施設でのフットケアのすすめ(2022/05/16)(嘉陽海子)
- 足底の角質肥厚部位の特徴と美容的観点から考えたフットケアについて(2022/03/10)(萩原直見)
- むくみの圧迫療法(2022/02/24)(原尚子)
- 足にむくみがあったら(2022/02/15)(原尚子)
- 女性アスリート問題から考える女性に起こりやすい体の問題(2022/01/13)(宮本由記)
- ランニングシューズの選び方(初級者)3-3(2021/12/14)(原田繁)
- ランニングシューズの選び方(初級者)2-3(2021/12/04)(原田繁)
- ランニングシューズの選び方(初級者)1-3(2021/11/29)(原田繁)
- 足の骨は扇型?(2021/10/27)(遠藤剛)
- 足は伸びる?(2021/10/20)(遠藤剛)
- 足の爪を爪切りでパチンパチンと切っていませんか?(平扶美子)
- 足の爪に使うヤスリの選択(2021/10/04)(平扶美子)
- 上履き選びのポイント(2021/09/13)(山口久美子)
- バレーシューズの問題点(2021/08/30)(山口久美子)
- 転倒した自分(2021/08/02)(吉田圭)
- まずは自分の靴を確認しよう! 靴の"型"による履歴と癖(2021/07/20)(山口宏二)
- 最近よく見る爪のトラブルと靴のサイズのこと(2021/07/07)(吉本錠司)
- 足の健康を守る歩き方(2021/06/24)(黒田恵美子)
- 靴のラストサイズか足入れサイズか(2021/06/09)(吉本錠司)
- "歩き支えるための"高齢者(シニア世代)の靴選び(2021/05/28)(大沼幸江)
- ゆるゆる屈伸のススメ(2021/05/10)(黒田恵美子)
- 足のトラブルと栄養の関係(2021/04/29)(齊藤瑠璃子)
- 足のトラブル予防とケア(2021/04/06)(齊藤瑠璃子)
- 浮き趾の原因と予防(2021/03/23)(金森慎悟)
- 外反母趾と運動(2021/03/09)(金森慎悟)
- 爪切り難民と爪甲除去(麻酔を要さない)60点(2020/09/04)(高山かおる)
- 靴の清掃・お手入れの方法(2020/06/25)(吉田圭)
- 洗えるマスクの配布にあたり(2020/05/27)(高山かおる)
- 高齢者の足事情(2017/11/30)(中西薫)
- 【イベント報告】横浜市皮膚科医会主催 市民公開講座(2017/06/14)(今井亜希子)
- ピュアフット15周年を迎えて(2016/12/22)(菊池晴香)
- 「あしラブ」習慣について(2016/11/01)(高山かおる)
- 靴底と歩き方(2016/10/24)(吉田圭)
- 転倒を防ぎ健康寿命を延ばす大腿筋力の重要性(2016/08/16)(金森慎悟)
- 足の健康診断「フットチェック」で見えてきたこと(2016/08/05)(上田暢彦)
- 足に合った靴選び(2016/07/27)(吉田圭)
- 姿勢と骨盤底筋の関係(2016/07/08)(金森慎悟)
- 「足病医が語る アメリカ流 巻爪の治し方」~ エプソムソルトでの「ソーキング」~(2016/07/04)(林美香)
- 0歳からの足育(2016/06/28)(玉島麻理)
- フットケアに出会って(2016/05/31)(高山かおる)
- 書籍紹介「Derma 243~皮膚科医が行う足診療~」(2016/04/25)(高山かおる)
- 「第14回日本フットケア学会」 参加レポート(2016/02/10)(高山かおる)
- トラブルのある足に義肢装具士がお答えします(2016/01/12)(山口宏二)
- 足から見た転倒予防に必要なこと(2015/11/24)(今井亜希子)
- 足が支える健康寿命(2015/11/11)(高山かおる)
- 歩く動作と足の関係について(2015/09/24)(黒田恵美子)
- フットケアの必要性(2015/08/28)(高山かおる)
- サイズ感覚の習慣(2015/07/30)(吉田圭)
- 足もとからの健康と靴選び(1)(2015/07/01)(大沼幸江)
- たかが足、されど足(2015/05/12)(林美香)